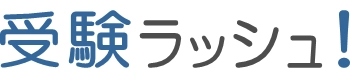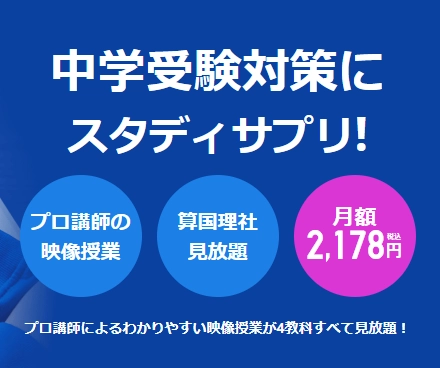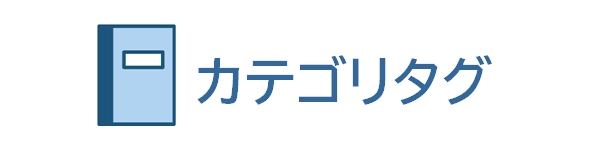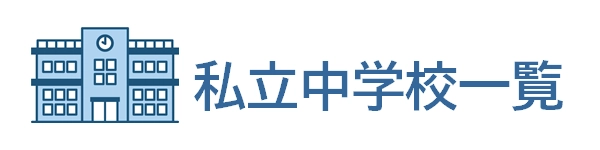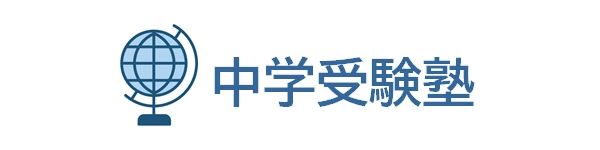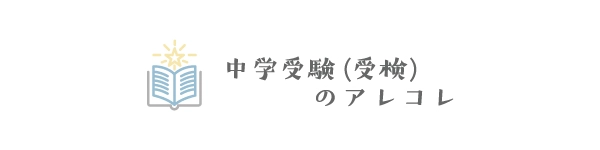19,578view
中学受験において受験校の過去問はどれくらい解くべきか?
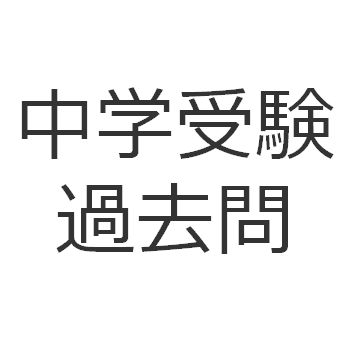
はじめに
中学受験において、これから(秋冬から)本番受験に向けて、
「過去問」
に本格的に取り組む時期となり、
「受験校の過去問はどれくらい解けばいいの?」
と、わからない方や悩む方も多いと思います。
そこで、
今回は、中学受験において受験校の過去問はどれくらい解くべきか?について、うちの経験を踏まえて色々と述べたいと思います。
[目次]
受験校の過去問はどれくらい解くべきか?
・過去問に対する考え方は人によって違う
・受験校の過去問をどれくらい解いたか?
・うちが過去問を解いた時期
・過去問1回目はかなり時間がかかる
受験校に対する過去問について
・麻布の過去問
・本郷の過去問
・浅野の過去問
・栄東(A日程)の過去問
・栄東(東大特待)の過去問
・渋幕の過去問
まとめると
最後に
受験校の過去問はどれくらい解くべきか?
・過去問に対する考え方は人によって違う
・受験校の過去問をどれくらい解いたか?
・うちが過去問を解いた時期
・過去問1回目はかなり時間がかかる
受験校に対する過去問について
・麻布の過去問
・本郷の過去問
・浅野の過去問
・栄東(A日程)の過去問
・栄東(東大特待)の過去問
・渋幕の過去問
まとめると
最後に
受験校の過去問はどれくらい解くべきか?
これまでも過去問に関する記事をいくつか書いていますが、先日、Twitterで、
「受験校の過去問はどれくらい解きましたか?」
というご質問をいただき、
思い返せば、今まで、
「受験校の過去問をどれくらい解いたか?」
について具体的に書いたことがないな?と思い、
今回、具体的に、うちが実際に受験した受験校の過去問をどれくらい解いたか?について書いている次第です。(はい)
ということで、
以下、中学受験において受験校の過去問はどれくらい解くべきか?についてのうちの経験と僕の考えです。
過去問に対する考え方は人によって違う
本題に入る前にお伝えしておきますが、中学受験における過去問に対する考え方や取り組み方針については、
「過去問は多く解いた方がいい」
という人もいれば、
「過去問はあまりやらなくてもいい」
という人もいます。
つまり、
・過去問に対する考え方
・過去問に対する取り組み方針
・過去問に対する取り組み方針
は、塾の方針や先生、親御さんによっても大きく違います。
そのため、
「過去問は何年分解くのが正しい」
といった正解はどこにもありません。
ということで、
この記事では、実際、うちが受験校の過去問をどれくらい解いたのか?を述べますが、
参考程度にご覧いただければと思います。
受験校の過去問をどれくらい解いたか?
まずは、うちが受験した学校に対して、実際、どれくらいの過去問を解いたか?(正確には解かせたか)は、以下のとおりです。
受験校
過去問
備考
麻布
10年分×2回
第一志望校
本郷
5年分×2回
実力相応校
浅野
5年分×2回
実力相応校
栄東(A日程)
5年分×2回
お試し校
栄東(東大特待)
5年分×1回
チャレンジ校
渋幕
0回
チャレンジ校
ちなみに、
初めてこのブログを見たという方に、念のため僕の自慢話をお伝えしておきますが、
上記の受験校には、
「全て合格」
しています。
ただし、
他の記事でも述べているように、
実際に受験した上記の学校以外にも、早稲田中、芝中などの過去問も解いており、
最初に解いた過去問(1回目)は、全ての学校とも最低点(合格点)に達していません。
[ご参考]
また、
過去問は人によって、解く量は違いますが、受験校以外の過去問も解いているので、
「うちは、過去問を解いた量としては多い方」
かもしれません。
うちが過去問を解いた時期
以前、他の記事でも述べていますが、うちが、本格的に過去問を解き始めたのは冬の12月からで、かなり遅い方だと思います。
[ご参考]
過去問は、一般的には10月頃から解き始めると言われている中で、
「過去問解き始めるの遅くない?」
と思う方も多いと思いますが、
うちが過去問を解き始めたのが遅い理由は、
ズバリ!
「受験校が決まっていなかったため」
という理由です。
また、
「短期間にかなりの過去問を解いたのでは?」
と思う方も多いと思いますが、
基本的には、
・冬休みの間
・中学受験で学校を休んでいる間
・中学受験で学校を休んでいる間
に、集中的に過去問を解いています。
[ご参考]
そういう意味では、
「12月~1月のほとんどの時間を過去問!」
に費やしたという感じです。
もちろん、
計算ドリル、漢字ドリルといった基本演習もやってはいましたが、
冬のほとんどの時間は、過去問と解説の理解に充てていました。
過去問1回目はかなり時間がかかる
過去問を解き始めると、「過去問って意外に時間がかかる」
と思う方も多いと思います。
先の記事でも述べていますが、
特に、
「過去問1回目はかなり時間がかかる」
ということは当たり前のことです。
実際、うちも過去問1回目は、かなりの時間をかけています。
もちろん、
過去問そのものを解く時間もそうですが、
解いたあとに、解説を理解するまでを含めると時間がかかるのは当然です。
受験校に対する過去問について
次から、うちが受験した学校の過去問について、学校別にもう少し詳しく述べます。
麻布の過去問
まずは、麻布中学校の過去問についてです。
麻布は、第一志望校であったということもあり、過去問は、全科目(国語、算数、理科、社会)
最低、
・10年分×2回
は、確実に解いています。
ここだけは、自信を持って断言します。
[ご参考]
また、
科目やあまり理解できていないような問題によっては、3回以上は解いています。
ご存知の方も多いと思いますが、
麻布の入試問題は、独特というか、難問、奇問が多いということもあり、麻布を第一志望校としている時点で、
「頼れるものは過去問しかない」
「過去問 = 志望校のテキスト」
といった感じで、
麻布の過去問には一番時間をかけています。
ちなみに、
うちが過去問を本格的に解き始めた最初の過去問も麻布の過去問です。
本郷の過去問
次に、本郷中学校の過去問についてです。
本郷は、併願校(実力相応校)であったということもありますが、
過去問は、
・5年分×2回
くらいは、解いています。
くらいと言っているのは、科目によっては、2回解いていない科目もあるかもしれません。
※スミマセン、今となっては正確には覚えていません...
また、
1月に渋幕に合格したということもあり、入学先は麻布か渋幕のどちらかと決めていたため、
渋幕に合格してから(1月後半から)は、麻布以外の過去問は、ほとんど解いていないというのが実態です。
[ご参考]
浅野の過去問
次に、浅野中学校の過去問についてです。
浅野も、併願校(実力相応校)であったということもありますが、
過去問は、
・5年分×2回
くらいは、解いています。
ただし、
本郷と同様に、渋幕に合格してからは、麻布以外の過去問は解いていないというのが実態です。
栄東(A日程)の過去問
次に、栄東中学校(A日程)の過去問についてです。
栄東(A日程)は、併願校とはいうものの、お試し校/腕試し校として受験したということもありますが、本番受験初戦ということもあり、
・5年分×2回
は、解いています。
やはり、
入学する可能性は低いにせよ、初戦は落としたくないので...
栄東(東大特待)の過去問
次に、栄東中学校(東大特待)の過去問についてです。
栄東(東大特待)は、初戦の栄東(A日程)の2日後が入試日であったことと、チャレンジ校であったということもあり、
・5年分×1回
くらいしか、解いていません。
というか、
解く時間がなかったというのが実態です。
渋幕の過去問
最後に、渋谷教育学園幕張中学校の過去問についてです。
このブログでも何度か述べていますが、
渋幕は、チャレンジ校として、本当に急に受験を決めたため、
過去問は、
・0回
つまり、
全く解かないで受験しています。
[ご参考]
というか、
急に受験を決めたということもあり、
過去問を準備する時間、解く時間がなかったのは当然ですが、
記念受験のつもりで、合格することも想定しておらず、かつ、2月校の過去問も終わっていないという状況で、2月校の過去問を重視したというのが実態です。
まとめると
うちが解いた過去問を学校の難易度/種類毎にまとめると、難易度/種類
受験数
過去問
第一志望校
1校
10年分×2回
実力相応校
2校
5年分×2回
お試し校
1校
5年分×2回
チャレンジ校
2校
5年分×1回、0回
となり、
第一志望校の過去問を一番多く解いたのは当たり前ですが、チャレンジ校の過去問が一番少ないという結果になっています。
最後に
今回、中学受験において受験校の過去問はどれくらい解くべきか?について、うちの経験を踏まえて色々と述べましたが、最初にも述べているように、過去問に対する考え方や取り組み方針は、塾や先生、親御さんによって大きく違います。
ただ、
僕としては、
実際に入学する可能性のある受験校の過去問は、
「最低2回は解く必要がある」
そうしないと、
「問題の傾向やクセは見えないのでは?」
と考えています。
いずれにせよ、
この記事、何か参考になれば幸いです。