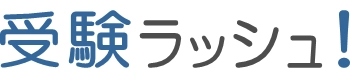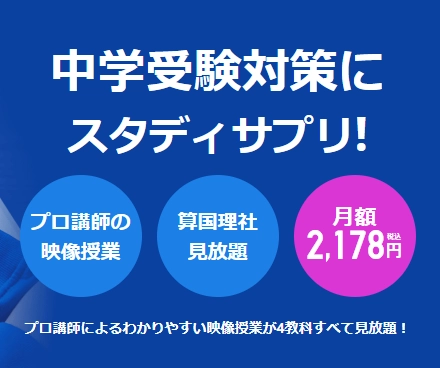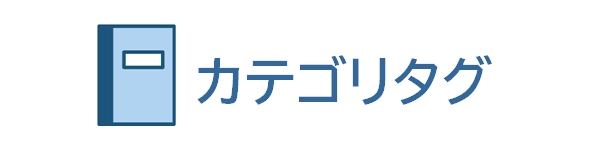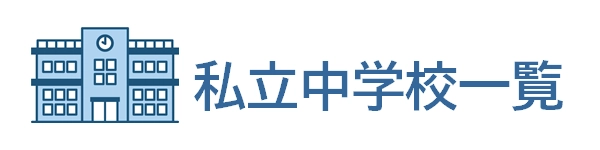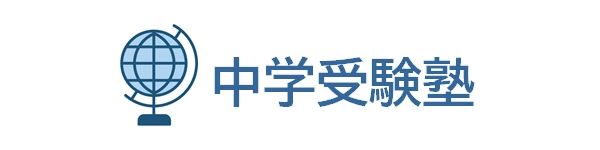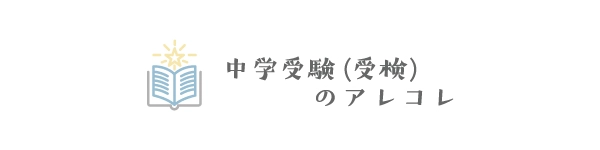34,733view
中学受験の過去問はいつから解き始めればよいのか?(遅くても大丈夫?)
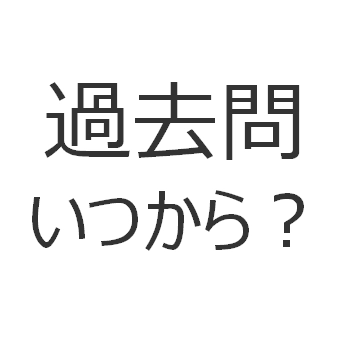
はじめに
中学受験において、本番受験に向けては、普段の受験勉強に加え、
志望校対策の一つとして、
「過去問」
を解く必要があります。
そのような中で、
「過去問はいつから解き始めればいいの?」
と悩む方も多いと思います。
そこで、
今回は、中学受験において過去問はいつから解き始めればよいのか?について、
うちの経験を踏まえて色々と述べます。
[目次]
うちが過去問で失敗したこと
過去問はいつから解き始めればよいのか?
・10月頃から解き始める?
・10月時点で志望校が決まっているか?
・1.第一志望校(確定) 併願校(確定)
・2.第一志望校(確定) 併願校(未確定)
・3.第一志望校(未確定) 併願校(確定)
・4.第一志望校(未確定) 併願校(未確定)
・10月に志望校が決まっていることが理想
過去問を解き始めるのは早すぎてもダメ
過去問に対する塾の方針は違う
過去問の解き始めが遅くても大丈夫?
最後に
うちが過去問で失敗したこと
過去問はいつから解き始めればよいのか?
・10月頃から解き始める?
・10月時点で志望校が決まっているか?
・1.第一志望校(確定) 併願校(確定)
・2.第一志望校(確定) 併願校(未確定)
・3.第一志望校(未確定) 併願校(確定)
・4.第一志望校(未確定) 併願校(未確定)
・10月に志望校が決まっていることが理想
過去問を解き始めるのは早すぎてもダメ
過去問に対する塾の方針は違う
過去問の解き始めが遅くても大丈夫?
最後に
うちが過去問で失敗したこと
中学受験において過去問はいつから解き始めればよいのか?を述べる前に、最初に、
「うちが過去問で失敗したこと」
について述べます。
このブログでも何度か述べていますが、
うちは、
息子の成績の浮き沈みというか波が激しく、
成績が全く安定せずに、
「志望校がなかなか決まらない」
という状況の中で、
過去問を本格的に解き始めたのが
「本番直前の12月に入ってから」
と、かなり遅くから解き始めました。
もちろん、
12月まで、全く過去問をやっていなかったわけではありませんが、
「本格的に解き始めたのは12月に入ってから」
でした。
そんな状況の中で、
突貫工事のように本番直前にあわてて受験校の過去問を解くという状況になり、
「もっと早くから始めればよかった」
と悔やんだ経験があります。
これが、うちが過去問で失敗したことです。
ということで、
これから、
うちの失敗を踏まえて、
中学受験において過去問はいつから解き始めればよいのか?について僕の考えを説明します。
過去問はいつから解き始めればよいのか?
以下、中学受験において過去問はいつから解き始めればよいのか?についてです。10月頃から解き始める?
ぶっちゃけ、「過去問をいつから解き始めればよいか?」
は、人によって違いますが、
一般的に、本格的に解き始めるのは、
本番受験の3~4ヵ月前である
「10月頃から解き始める」
とよく言われており、
僕も10月頃から解き始めるという考えを否定するつもりは一切ありませんし、
「10月頃から始めることが理想」
だと考えています。
※あくまでも理想です。
実際、
御三家を初めとする人気校については、過去問が出版されるのは早いですが、
最終的に出版社から過去問が全て出版されるのは9月末~10月初となっており、
まさに、
秋から過去問を解き始めるのに合わせた感じとなっています。
[ご参考]
ただし、
これは、
あくまでも、
「過去問を解き始める時期だけの話」
であり、
10月頃から解き始めると言われると、
「志望校が決まっていないけどどうしよう?」
と焦ってしまう方も多いと思います。
何を言いたいのかというと、
志望校が決まっていない中で、
「闇雲に本格的に過去問を解いても仕方がない」
ということです。
特に、
9月から11月にかけて頻繁に模擬試験が開催されるため、
模擬試験の結果によって志望校、最終的には受験校がなかなか決められないという状況の方も多いと思います。
※うちがまさにそうでした...
10月時点で志望校が決まっているか?
先で、過去問を解き始めるのは10月頃からというのが一般的であると述べていますが、そもそも、現実的には、
ある程度、
「志望校が決まってから解き始める」
ということも大前提になります。
やはり、
受験生も受験生の親も、
志望校がある程度決まらないうちに、闇雲に色んな学校の過去問も解いたとしても、混乱したり、全く解けなかったりするとモチベーションが下がってしまう
ということが起きてしまうため、
中学受験においては、過去問を本格的に解き始める時期には注意が必要です。
そういう意味では、
・過去問を解き始める時期
・志望校を決める時期
・志望校を決める時期
は切っても切り離せない関係です。
また、
志望校の中にも、
大きくは、
・第一志望校
・併願校(実力相応校、安全校、お試し校)
・併願校(実力相応校、安全校、お試し校)
があり、
僕の考えでは、10月時点で第一志望校、併願校がある程度決まっているか否かで、
過去問を解き始める時期は、下表の4つのケースとなります。
▽過去問の開始時期
ケース
第一志望校
併願校
過去問の開始時期
1
確定
確定
9月~10月から
2
確定
未確定
10月から
3
未確定
確定
10月から
4
未確定
未確定
志望校確定後
一応、補足しておきますが、
あくまでも、
志望校が決まっているか否か(確定しているか否か)であり、実際に受験する受験校が決まっているか否かではありません。
上表でいう「確定」とは、
例えば、
実際に受験するかは別にして、志望校として、第一志望校は2校、併願校は7校など、ある程度決まっている(絞っている)という状態です。
そして、
それぞれのケースにおける過去問の開始時期については、以下のとおりです。
1.第一志望校(確定) 併願校(確定)
ケース
第一志望校
併願校
過去問の開始時期
1
確定
確定
9月~10月から
ケース1は、既に第一志望校は確定、併願校も確定しているというケースです。
このケースの場合は、早ければ9月から、本格的には10月から第一志望校、併願校ともに過去問を解き始めてもよいと考えています。
そういう意味では、
志望校が決まっているということもあり、9月頃から過去問を解き始めてもよいとは思いますが、
9月からは、模擬試験が頻繁に開催される時期に入るため、
どちらかというと、
過去問よりも模擬試験で弱点を見つけ出すことに注力した方がよいと考えています。
2.第一志望校(確定) 併願校(未確定)
ケース
第一志望校
併願校
過去問の開始時期
2
確定
未確定
10月から
ケース2は、10月時点で第一志望校は確定、併願校は未確定というケースです。
このケースの場合は、第一志望校が決まっているということもあり、第一志望校の過去問を解き始めてもよいと考えています。
ちなみに、
第一志望校が決まっており、併願校が決まっていないというこのケースが一番多いケースだと思います。
3.第一志望校(未確定) 併願校(確定)
ケース
第一志望校
併願校
過去問の開始時期
3
未確定
確定
10月から
ケース3は、10月時点で第一志望校は未確定、併願校は確定しているというケースです。
このケースの場合は、併願校が決まっているということもあり、併願校の過去問を解き始めてもよいと考えています。
ちなみに、
第一志望校が決まらずに、併願校が決まっているというこのケースは、あまりないケースだと思いますが...
4.第一志望校(未確定) 併願校(未確定)
ケース
第一志望校
併願校
過去問の開始時期
4
未確定
未確定
志望校確定後
ケース4は、10月時点で第一志望校は未確定、併願校も未確定というケースです。
このケースの場合は、第一志望校も併願校も決まっていない状態で、そもそも、過去問を解き始めることはできないと考えています。
ちなみに、
このケースは、
「まさにうちのケース」
であり、
10月時点で第一志望校も併願校も決まっていないというケースは、意外にも多いのでは?とも考えています。
10月に志望校が決まっていることが理想
そもそも、受験生や受験生の親も、
受験を少しでも考えている学校の過去問を、本格的に解くまでにはいかないまでも、
少し解いてみたり、既にある程度見ているという方も多いと思います。
早い話が、
「志望校選びに過去問を活用している」
ということです。
つまり、
色んな学校の入試問題を研究しながら、学校選びをしている方も多いと思います。
もう少しいうと、
この学校とこの学校は問題の傾向や質が違うため併願は厳しいとかを判断するためにです。
実際、うちは、志望校選びのために、少しでも受験を考えたことがある学校の過去問は全て購入しており、
正直、何冊買ったかわからないくらいに家に過去問があります...
そう考えると、
なかなか志望校や併願校が決まらないというのが現状であり、
「志望校選びは中学受験の大きな悩みの一つ」
です。
ただし、
「過去問はかなり時間がかかります」
過去問を単に解くだけであれば、それほど時間はかかりませんが、
本格的に解いて、内容を理解するためには、かなり時間がかかります。
ちなみに、
僕が推奨する過去問を解く量は、
志望校
過去問
第一志望校
10年分×2回(最低でも)
併願校
5年分×2回(最低でも)
であり、
これだけの量を解くには、やはり、時間がかかります。
[ご参考]
また、
入試問題は学校によっては色んなクセがあるため、受験を少しでも考えている志望校の過去問を解いてみて、
自分に合うような問題が出題される学校を選ぶということも、時には必要になります。
そう考えると、
やはり、過去問は、
「10月頃から解き始める」
というのが理想であり、
偏差値が届いている、届いていないはさておき、
「10月に志望校が決まっていること」
が理想だと考えています。
※あくまでも理想です...
過去問を解き始めるのは早すぎてもダメ
先で、中学受験においては、過去問を解き始めるのは10月頃というのが一般的であり、僕も10月から解き始めるのが理想であると述べていますが、
ここで、
既に志望校が決まっている方としては、
「もっと早くから解き始めてもよいのでは?」
という方もいると思います。
もちろん、
志望校が既に決まっており、塾の勧めや受験生、親の判断によっては、その志望校の過去問を早い段階から解くような場合もあると思います。
ただし、
あまりにも早い時期から過去問中心の勉強をしてしまうと、
何回か過去問を解いていくうちに、
「受験生である子供は答えを覚えてしまう」
ということになってしまい、
過去問で志望校対策をする上で、
「弱点が見えなくなってしまう」
という懸念があります。
そのため、
過去問は基礎が整い
「ある程度の応用力がついてから」
解き始めた方がよいと僕は考えています。
そういう意味では、
たとえ志望校が決まっていたとしても、
過去問を解き始めるのは、
「早すぎてもダメ」
です。
また、
過去問を早く解き始めたとしても、解けないのは当たりのことですが、
ある程度の応用力がついてから解き始めても、最初解けないのは当たり前のことです。
[ご参考]
過去問に対する塾の方針は違う
ご参考までに言っておきますが、塾によっては、
「過去問に対する方針が全く違う」
ということが、多々あります。
もう少し言うと、
過去問を推奨していないというか、過去問を解くこと、過去問中心の受験勉強をすることに否定的な塾もあります。
もちろん、
塾のクラスや先生、時期によっても違うとは思いますが...
いずれにせよ、
過去問を全く解かないで受験する受験生は、ほとんどいないと思いますが、
過去問は量もある程度は大事ですが、このブログでも何度か述べているように、
志望校の入試問題に関する情報は、過去問しかないため、
「過去問 = 志望校のテキスト」
と捉えて解き方を理解することが何よりも重要だと僕は思います。
過去問の解き始めが遅くても大丈夫?
最後に、10月になっても、
「志望校が決まっていない」
つまり、
「過去問を解き始めたくても始められない」
という方のために、補足しておきます。
最初で、
うちが中学受験において、過去問で失敗したこととして、
「過去問を解き始めるのが遅かった」
と述べていますが、
今思えば、
本格的に過去問を解き始めたことが遅かったこと全てが失敗かというと、全くそんなことはなく、
解き始めが遅い利点もありました。
それは、
本番直前の冬の短い期間に、
・集中して過去問を解いたこと
・過去問中心の受験勉強をしたこと
・過去問中心の受験勉強をしたこと
により、
最終的には、麻布、渋幕をはじめ、受験校全てに合格できています。
[ご参考]
入試日
学校
結果
1月10日
栄東中学校(A日程)
合格
1月12日
栄東中学校(東大特待クラス)
合格
1月22日
渋谷教育学園幕張中学校(一次入試)
合格
2月1日
麻布中学校
合格
2月2日
本郷中学校(第2回)
合格
2月3日
浅野中学校
合格
だからといって、
過去問を本番直前のギリギリまで解かなくてもいいと言いたいわけではありませんが、
他の受験生より、遅く始めたからといって、簡単に諦めることはないです。
最後に
今回、中学受験において過去問はいつから解き始めればよいのか?について、うちの経験を踏まえて色々と述べましたが、
先で述べているとおり、
過去問というか入試問題は、学校によって本当にクセがあります。
それを見極めるためにも、やはり秋ぐらいから徐々に本格的に過去問を解き始めるのが理想的だと思います。
最後に、
皆さん、うちのように、志望校がなかなか決まらずに、突貫工事のように本番直前にあわてて受験校の過去問を解くようなことがないように注意しましょう
ということをお伝えしたいのと同時に、
解き始めが遅いからといって、諦めることは全くなく、
本番直前の冬の短い期間に、
・集中して過去問を解くこと
・過去問中心の受験勉強をすること
・過去問中心の受験勉強をすること
でも、
「合格を手にすることはできる」
ということを言いたいです。