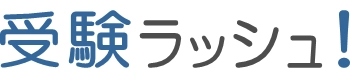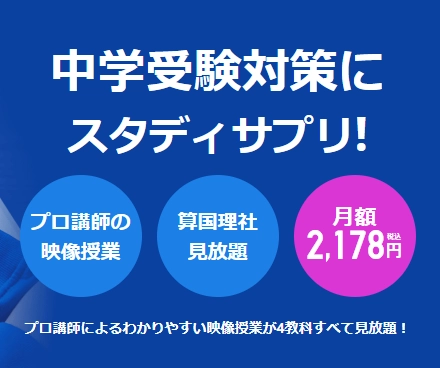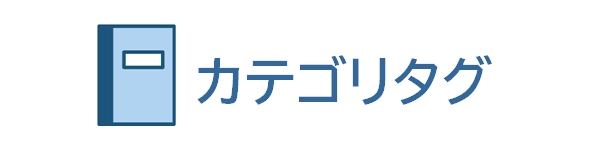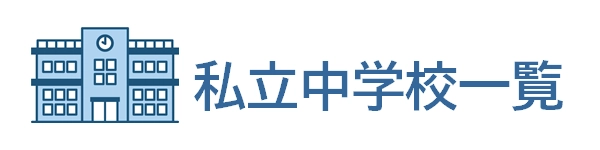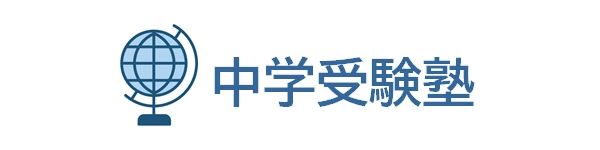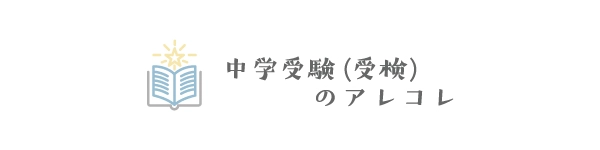48,719view
中学受験における難関校、中堅校ってどこの学校?実は定義が存在しない!

はじめに
中学受験において、「難関校、中堅校」
という言葉に触れる機会も多いと思いますが、
「具体的にどこの学校?」
という疑問を持ったことはないでしょうか?
実は、
「難関校、中堅校の定義は存在しない!」
というのが実態です。
そこで!
今回は、中学受験において難関校、中堅校の定義が存在しない理由について、僕の考えを色々と述べたいと思います。
[目次]
難関校、中堅校の定義は存在しない!
難関校、中堅校の意味について!
・難関校とは?
・中堅校とは?
難関校、中堅校の定義が存在しない理由!
・1.偏差値は塾や模擬試験によって違う!
・2.複数回受験校の偏差値!
・3.偏差値は毎年変動する!
難関校、中堅校を分別するとしたら?
最後に
難関校、中堅校の定義は存在しない!
難関校、中堅校の意味について!
・難関校とは?
・中堅校とは?
難関校、中堅校の定義が存在しない理由!
・1.偏差値は塾や模擬試験によって違う!
・2.複数回受験校の偏差値!
・3.偏差値は毎年変動する!
難関校、中堅校を分別するとしたら?
最後に
難関校、中堅校の定義は存在しない!
中学受験において「御三家」というと、男子校の場合は、
女子校の場合は、
と、明確に学校名がわかります。
ただし、
最初でも述べているように、
「難関校って具体的にどこの学校?」
「中堅校って具体的にどこの学校?」
という疑問が出てくる方も多いと思います。
最初に結論を言うと、
世の中に
「難関校、中堅校の定義は存在しない!」
というのが現状です。
※現状というか、将来も定義されることはないと思います...
また、僕もそうですが、色んな記事を見ても、何となくのニュアンスで使用しているというのがほとんどです。
ということで、
これから、難関校、中堅校の定義が存在しない理由について、僕の見解を踏まえて説明します。
難関校、中堅校の意味について!
まずは、中学受験における難関校、中堅校の意味についてです。難関校とは?
一応、念のため、「難関校」について調査してみました。「難関校」を辞書で調べてみると、
入学試験の難度が高い学校
と記載されています。
確かに、そのとおりですが、「難度が高い学校」が曖昧です。
また、「難関校」を使っている色んな記事を見てみると、男子校であれば、「筑駒、開成、麻布などの難関校」、女子校であれば、「桜蔭、女子学院などの難関校」という表現をしているものが多く、「などの難関校」がやはり明確にはなっていません。
中堅校とは?
次に、「中堅校」についても調査してみました。「中堅校」を辞書で調べてみると、「中堅校」そのものは辞書には載っていませんでしたが、「中堅」には色んな意味があり、
読んで字のごとく、
真ん中、中くらい
という意味で記載されています。
また、「中堅校」を使っている色んな記事を見てみても、やはり、具体的な学校を記載している記事はなく明確にはなっていません。
それを踏まえて、難関校、中堅校の定義が存在しない理由について説明します。
難関校、中堅校の定義が存在しない理由!
そもそも、仮に学校を
・難関校
・中堅校
・中堅校
に分別するとした場合に、
「何を基準に分別するか?」
という問題が出てきます。
その際に出てくる基準の中には、やはり、
「偏差値」
があります。
ただし!
偏差値では、難関校、中堅校を分別できない、
大きくは、
という3つの理由というか問題があります。
次から、それぞれの理由(問題)について説明します。
1.偏差値は塾や模擬試験によって違う!
偏差値は、塾や模擬試験によっても違うため、単純に偏差値では学校を評価できないという問題があります。[ご参考]
例えば、
といった塾によっても偏差値は違いますし、
といった模擬試験そのものや、同じ塾の模擬試験でも実施する種類や回(時期)によっても偏差値は変わってきます。
具体的には、模擬試験を受ける受験生の学力、志望校によって偏差値は変わってきます。
そのため、偏差値で難関校、中堅校を分別しようとした場合、どの偏差値を基準に難関校、中堅校を分別するのか?という問題があります。
2.複数回受験校の偏差値!
中学受験には一回受験の学校(一回受験校)と複数回受験の学校(複数回受験校)があります。[ご参考]
一回受験校の偏差値は、学校の偏差値と直結しますが、複数回受験校の偏差値は、試験によって変わってくるため、一概に学校の偏差値とは言えないという問題があります。
例えば、複数回受験校の単純な例として、
・第1回入試:偏差値50
・第2回入試:偏差値60
・第3回入試:偏差値70
・第2回入試:偏差値60
・第3回入試:偏差値70
という学校がある場合、学校としての偏差値は、どの回の偏差値が学校の偏差値となるのか?
つまり、
・一番低い偏差値(50)?
・一番高い偏差値(70)?
・平均の偏差値(60)?
・一番高い偏差値(70)?
・平均の偏差値(60)?
ということになってしまいます。
そのため、一回受験校と複数回受験校の偏差値を求める(決める)基準が変わってくるという問題もあります。
3.偏差値は毎年変動する!
偏差値には、大きくは、
・模擬試験結果から算出された予想偏差値
・入試結果から算出された入試結果偏差値
・入試結果から算出された入試結果偏差値
の2つがあります。
仮に偏差値で難関校、中堅校を分別する場合は、予想偏差値はあくまでも予想なので入試結果をもとにした偏差値が一番いいと僕は考えています。
ただし、
予想偏差値は、先でも述べているように、塾や模擬試験の回によって変わるのと同じように、入試結果偏差値も同じように受験生の学力によって毎年変動します。
そのため、仮に偏差値で難関校、中堅校を定義したとしても、偏差値は、毎年変動するため、難関校、中堅校の定義も毎年変動してしまうという問題もあります。
難関校、中堅校を分別するとしたら?
先で説明しているように、偏差値を基準に難関校、中堅校を分別することは難しいですが、仮に他の何かを基準に学校を分別する場合でも、
「やはり偏差値しかないのでは?」
と僕は思います。
ここで、
仮に難関校、中堅校を分別する際に、偏差値しかないと言っていますが、
「じゃ、何の偏差値を基準にするの?」
と言いたくなると思います。
これは、僕の勝手な見解ですが、予想偏差値はあくまでも予想なので、やはり、入試結果をもとにした
「入試結果偏差値が一番いい!」
と考えています。
※しつこいようですが、仮に難関校、中堅校を分別するとした場合の僕の考えです。
そのような中で、首都圏模試をはじめ、入試結果の偏差値を公開している塾も色々ありますが、その中でも一番、僕のイメージに近いというか、しっくりくるのが、
日能研が公開している
「中学入試結果R4一覧」
という偏差値一覧です。
また、先でも述べているように、複数回受験校については、2回目以降の実質倍率、偏差値が高くなるのは当たり前のことなので、あくまでも、1回目の偏差値を基準にするのが妥当だと考えています。
そして、
この「中学入試結果R4一覧」の偏差値を基準に首都圏の難関校、中堅校を分別したとすると、僕のイメージでは、
区分
男子校
女子校
共学校
超難関校
65以上
65以上
65以上
難関校
60-64
60-64
60-64
中堅校
50-59
50-59
50-59
のようなイメージになると思います。
しつこいようですが、あくまでも僕の考えです。
ちなみに、「難関校」は、僕の中では、
難関校の種類
説明
最難関校
難関校の中で最も偏差値の高い学校
超難関校
難関校の中でも偏差値の高い学校
難関校
上記以外の難関校
の3つに分かれ、僕もそうですが、最難関校、超難関校という表現を使っている方も多くいます。
例えば、首都圏では、
・筑駒は最難関校
・開成は私立の最難関校、もしくは、超難関校
・麻布は超難関校
・桜蔭は女子の最難関校、もしくは、超難関校
・女子学院は超難関校
・開成は私立の最難関校、もしくは、超難関校
・麻布は超難関校
・桜蔭は女子の最難関校、もしくは、超難関校
・女子学院は超難関校
という感じです。
また、難関校を「上位校」と表現している方も多くいます。
最後に
今回、中学受験において難関校、中堅校の定義が存在しない理由について、色々と述べましたが、難関校は大体想像がつきますが、中堅校の定義はやはり難しいです。いずれにせよ、どこまでが難関校で、どこまでが中堅校かは、人によって捉え方が違います。
余談ですが、いつもは、新規記事を書くときは、大体1週間くらいかかるのですが、この記事は、なぜか2週間かかっています。
やはり、定義がない曖昧なことを記事にすることは難しいです...
いずれにせよ、何かの参考になれば幸いです。