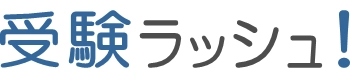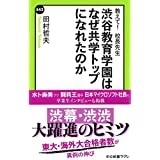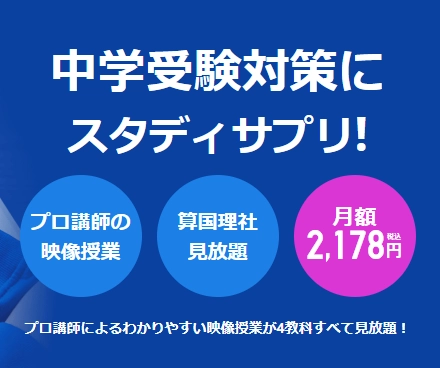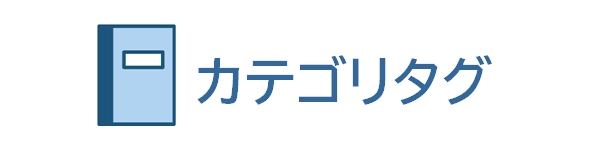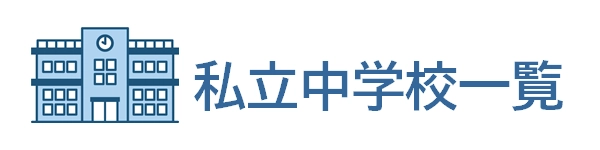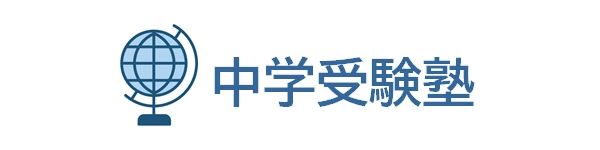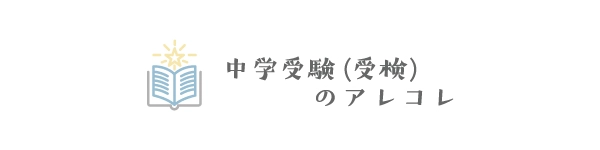33,662view
麻布と渋幕の深い関係と共通点/相違点について解説します!

はじめに
中学受験において、超難関校、かつ、人気校でもある
「麻布と渋幕」
には、実は、
「深い関係!」
というか繋がりや共通点があります。
※既にご存知の方も多いとは思いますが...
そこで!
今回は、麻布と渋幕の深い関係や共通点/相違点について、色々と述べたいと思います。
ちなみに、
うちの息子は、麻布と渋幕を受験し合格しています。
[目次]
麻布と渋幕の深い関係について!
・渋幕の校長は麻布出身である!
・渋幕の校長は麻布の理事である!
麻布と渋幕の共通点/相違点について!
・麻布と渋幕の共通点!
・麻布と渋幕の相違点!
ご参考!
最後に
麻布と渋幕の深い関係について!
・渋幕の校長は麻布出身である!
・渋幕の校長は麻布の理事である!
麻布と渋幕の共通点/相違点について!
・麻布と渋幕の共通点!
・麻布と渋幕の相違点!
ご参考!
最後に
麻布と渋幕の深い関係について!
これから、の2つの学校の深い関係や共通点/相違点について説明しますが、
念のため補足しておくと、
麻布は御三家、渋幕も千葉の御三家です。
[ご参考]
ということで、
以下、麻布と渋幕の深い関係についてとなり、
大きくは、
という2つについて、説明します。
渋幕の校長は麻布出身である!
麻布と渋幕が深い関係である1つ目は、「渋幕の校長は麻布出身である!」
という点です。
色んな業界に麻布出身の有名人、著名人は多数いますが、
渋幕の理事長、校長である、
田村哲夫(たむら てつお)氏
は、実は、
「麻布高校出身!」
です。
渋幕の田村哲夫校長は、1954年(昭和29年)に麻布高校を卒業。
その後、東京大学法学部に進学し、卒業後、銀行を経て学校法人渋谷教育学園の理事長となり、
現在は、渋谷教育学園渋谷中学校、渋谷教育学園幕張中学校の理事長、校長を務めています。
また、
渋幕を短期間で、東大をはじめとする超難関大学への合格者を多数出す、日本でもトップクラスの進学校に育てたのも田村哲夫校長であると言われています。
田村哲夫校長が書いた
という本も有名です。
※もちろん、うちにもあります。
そして、
田村哲夫氏が創立し育てた渋幕は、
2017年から、ついに、これも超短期間で東大受験専門指導塾である「鉄緑会」の指定校になっています。
というか、
東大をはじめとする超難関大学への合格者を多数出す渋幕を、さすがに鉄緑会も放っておけなかったのだと僕は思います。
[ご参考]
まっ、とにかく、
「田村哲夫氏は日本の教育者としては凄い方!」
です。(もちろん僕も尊敬しています。)
[ご参考]
渋幕の校長は麻布の理事である!
麻布と渋幕が深い関係である2つ目は、「渋幕の校長は麻布の理事である!」
という点です。
先で、渋幕の田村哲夫校長が麻布高校出身ということを述べましたが、
麻布高校出身ということだけではなく、1975年(昭和50年)から、渋渋、渋幕の理事長、校長を務めながら、
「母校である麻布学園の理事!」
も務めています。
どのような経緯で麻布の理事になったのかは、詳細は不明ですが...
このように、
田村哲夫氏を通じて、麻布と渋幕は意外にも、深い関係があり繋がっています。
麻布と渋幕の共通点/相違点について!
次に、麻布と渋幕の共通点/相違点について説明します。麻布と渋幕の共通点!
麻布というと、「自由で校則がない学校!」
で有名ですが、
実は、
渋幕も自由の中で
「自調自考」
という自分で調べて、自ら考えるという、教育方針であり、生徒に自由を委ねるという意味では、麻布の「自由」と共通する部分が多々あります。
また、校則についても、渋幕にもほとんどないことなど、学校方針や理念において共通することが多々あります。
実際、田村哲夫校長へのインタビュー記事などを見てみると、
渋幕を創立する際に、
麻布で学んだことが大変参考になった。
生徒の自主性を重んじる自由な校風の学校を作りたいと思っていた。
生徒の自主性を重んじる自由な校風の学校を作りたいと思っていた。
と述べています。
このように、教育方針や理念などにおいても、
「麻布と渋幕には共通点!」
が多くあり、繋がっているように感じ取れます。
麻布と渋幕の相違点!
先に、麻布と渋幕の共通点を述べましたが、もちろん、相違点もあります。例えば、
麻布には制服はなく、服装は自由ですが、渋幕には制服があるなどの相違点はありますが、
僕が考える一番の大きな相違点は、
渋幕には「シラバス」がありますが、麻布には「シラバス」がない!
という点です。
[ご参考]
いずれにせよ、
麻布と渋幕には多くの共通点はありますが、それぞれの学校のよさを活かした相違点もあります。
あとは、
どうでもいいことですが、
うちの息子曰く、麻布の机と椅子は、普通の学校によくある机と椅子ですが、受験のときに訪れた渋幕の机は機能性がある綺麗な机と椅子だったと言っていました...
早い話が渋幕の机はよかったと...
ご参考!
以前、他の記事でも述べていますが、うちの場合は、麻布の本番受験前に渋幕に合格していたということもあり、麻布が不合格だった場合は、渋幕に入学させるつもりでいました。
[ご参考]
もちろん、息子も麻布が不合格だったら渋幕に入学したいと言っていました。
今思えば、やはり、受験生である子供にも、麻布と渋幕には、目には見えない何か相通ずるものがあったからだと考えています。
最後に
今回、麻布と渋幕の深い関係について色々と述べたように、渋幕の校長が麻布高校出身であるということや、渋幕の校長が麻布の理事も務めているということもありますが、
いずれにせよ、
意外なところで、
「麻布と渋幕は関係があり繋がっています!」
ちなみに、
今回のこの記事ネタは、うちの息子が受験のときに家内から聞きましたが、
僕は当時、
「へーそーなんだー」
と思っていましたが、
こうして記事にしてみても、あまり思いは変わっていません。
皆さんも、
同じように「へーそーなんだー」と感じるとは思いますが、何かの参考になれば幸いです。
以上です。